
 |
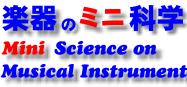 バイオリン の ミニ科学 続き |
![]()
弦をはじいて弾く楽器は沢山あります。 ギターはその代表例。 ギターの弦を弾いた時、音は相当長い間 「ポォーン」と鳴っています。
でも、バイオリンの弦を指ではじいて弾く、ピッチカート だと、「ポン」と直ぐに音は止まってしまいます。
なぜなんでしょうか。
その辺にも、バイオリンがバイオリンの音を出す秘密が隠されています。
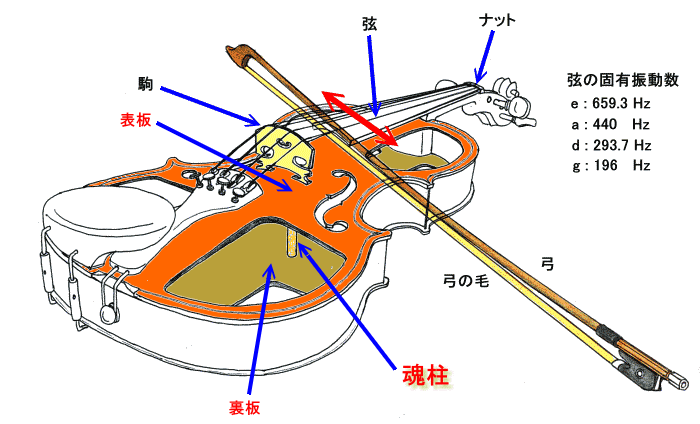
前の章でも触れましたが、
表板に載って立てられている駒のもう一本の足元の近くには、表板と裏板の間に、突っ張って立てられている細い木の 魂柱 と言う棒が立てられています。
バイオリンがバイオリンらしい音を出せるのは、この 魂柱 が有るからなのです。
(注)ギターには、魂柱のような棒はありません。胴の中は空気が詰まっているだけです。
魂柱 の役割は、表板の振動を裏板に伝達する働きがあります・・・と、簡単に説明されていますが、 逆に考えれば、裏板の振動を表板に伝達する・・・と言う役割も負っています。
すなわち、表板と裏板の振動を、相互に伝え合っている・・・と言うのが、正確な表現だとおもいます。
これを、絵にして見ましょう。
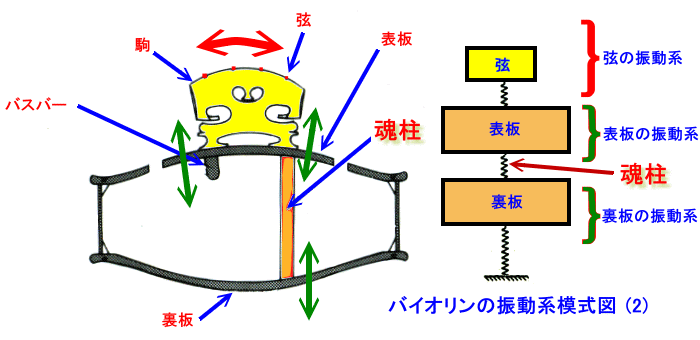
上の、バイオリンの振動系模式図(2) を、前章の図 と較べてみてください。 今回の図は、胴の振動系 の部分を、 表板の振動系 と 裏板の振動系 に分けてみました。
表板の振動系 と 裏板の振動系 は、魂柱 で繋がれています。
実際のバイオリンを考えるときは、このように、違った振動系がある・・・と分けて考えたほうが良く分かります。
バイオリンの表板、裏板は、材料や厚さ、隆起の形状、更には、表板には f字孔があけられていたり、バスバーが貼り付けられていたり・・・表板、裏板は違った振動特性を持っています。
バイオリンを製作するときは、それらを総合的に考えて、最も良い条件になるように、表板、裏板を削って作ります。
その様子は、こちらでご紹介しています、The Art of Violin Making などの文献にも紹介されています。
表板、裏板を削って、厚みを調整する方法の最も一般的な方法は、板を指で叩いて、その時の振動の音 から、板厚を調節する タップトーン などです。
いずれにしても、表板、裏板の振動特性を調節しながら作って行きます。
ここで、大切なことがあります。
表板 と 裏板 の固有振動数は、少しずらさなくてはならない 一見、不思議に思えるかも知れませんが、これは本当です。
通常は、表板は、軽いスプルース材、 裏板は、堅いメイプル材 で作られますので、黙っていても、裏板の固有振動数の方が、少し高い値になりますが、その、相互のずれの値をどのようにするか・・・
これが、バイオリン作りの極意 なのです。
さて、上のバイオリンの振動系模式図(2) を、もう一度ご覧下さい。
二つ あるいは、それ以上の振動系が繋がれて、一連の振動をしているときに、もし、そのなかに同じ固有振動数の振動系があった場合、それらは、互いに共振 しあって、大きな振動となる・・・と考えられますが、それは、振動系に外からエネルギーが注ぎ込まれて無い、自由振動 の場合のことです。
ところが、バイオリンの場合は、前章でも述べましたが、
バイオリンの弦は、弓の摩擦力から何らかのエネルギーを貰って、振動を続けている・・・と言いましたが、その振動が伝わってゆく
バイオリンの表板や裏板は、自由振動 では無く、弓の摩擦力から何らかのエネルギーを貰って、振動を続けているバイオリンの弦の振動によって、強制的に振動させられている・・・ということになります。
すなわち、バイオリンの表板や裏板は、強制振動 させられているのです。
このような振動系に於いて、もし、表板 と 裏板 の固有振動数が同じだった場合、ちょっと難しい言葉になりますが、「それらの位相は逆になり」 お互いの振動を打ち消しあってしまう・・・と言う現象が起こります。 (注)位相とは、力の向く方向・・・と考えて下さい
事実、バイオリンの表板と裏板の固有振動数をぴったり合わせたものを作ったら、大変弾き難く、又、音もかすれかすれになってしまうバイオリンになります。
そこで、
表板 と 裏板 の固有振動数を、少しずらして作られている 訳けです。
バイオリンの 魂柱 は、このように、固有振動数の少し違う振動系を相互につなぎ合わせているパーツなのです。
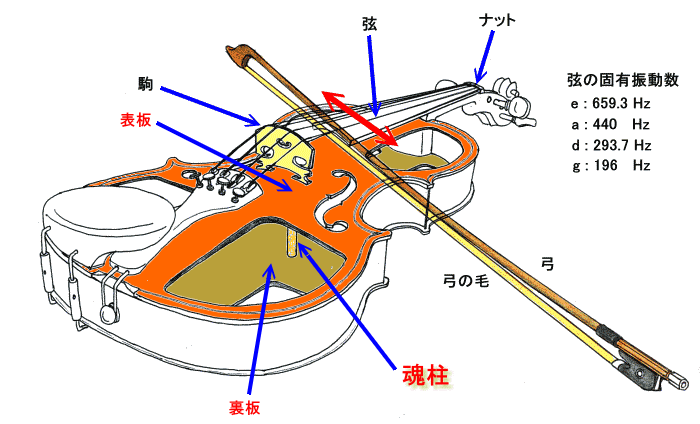
表板 と 裏板 の固有振動数が少しずれている・・・といっても、それらの位相は逆向きになっていますので お互いの振動を打ち消しあう・・・と言う現象は、なお存在します。
前章で、
摩擦力を持つ別な物体 で、弦を擦り続けていれば、駒や胴を振動させるエネルギーや空気を振動させるエネルギー分だけを、弓から供給してやれば、弦は振動し続ける・・・と言う事になります。
と、述べましたが、
正確には、
表板 と 裏板 の振動から生ずる、お互いの振動を打ち消しあう・・・力に負けないように、頑張って 必要なエネルギーを、弓から供給してやれば、弦は振動し続ける
と言う事になります。
冒頭で、
弦をはじいて弾く楽器は沢山あります。 ギターはその代表例。 ギターの弦を弾いた時、音は相当長い間 「ポォーン」 と鳴っています。
でも、バイオリンの弦を指ではじいて弾く、ピッチカート だと、「ポン」 と直ぐに音は止まってしまいます。
なぜなんでしょうか。
と書きましたが、もうお分かり頂けたとおもいます。
ピッチカート の時は、弾いたあとは何もエネルギーは供給されていません。
その時にも、表板 と 裏板 の振動から生ずる、お互いの振動を打ち消しあう・・・力 は働いてしまいますので、表板、裏板の振動が直ぐに止まってしまうのです。
一方、ギターのような、胴の中味が空っぽの、空気の詰まった楽器には、魂柱 のような棒はありません。 従って、表板、裏板 相互の振動を打ち消しあってしまうような現象は起こらないのです。 そのため、一度始まった振動が、ずぅーと 長続きして、 「ポォーン」 と鳴り続けるのです。
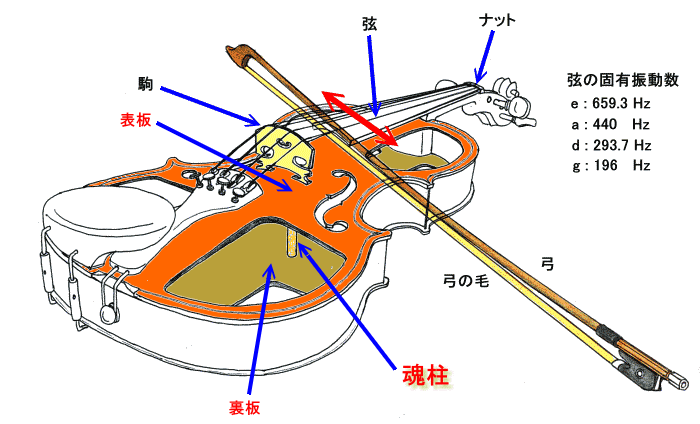
この絵のように、表板、裏板の一部を切り取ってしまったバイオリンでも、魂柱 が立っているバイオリンであれば、
魂柱 は、表板 と 裏板 の振動から生ずる、お互いの振動を打ち消しあう・・・相互作用 の仲介の役割をちゃんと果たしてくれています。
これが、バイオリンの演奏感覚を生み出してくれていますので、
弓 に、有る程度のエネルギー を与えながらの演奏・・・これは、魂柱 が立っているバイオリン ならでは出来ることなのです。
念のために
お互いの振動を打ち消しあう・・・相互作用 と書きましたが、 お互いの振動を打ち消しあって 鳴らなくなってしまうのでは・・・と思われるかも知れませんが、心配は要りません。
ボーイングの基本が出来ていて、弓の圧力やスピードがチャンとコントロールできれば、
それによって、バイオリンの表板や裏板は目一杯 強制振動 させられますので、力強く振動 してくれます。
要は、お互いの振動の打ち消しあい に負けない、ボーイング・・・をトレーニングされることが、肝心です。
以上、バイオリンの音の出る仕組み と、バイオリンの構造の違いによる音の出方 について簡単に解説して参りました。
あなたが、どのバイオリンを使うか・・・は、目的に従って選んで下さい。
| バイオリン の ミニ科学 トップページへ戻る |
工房ミネハラ
Mineo HaradaUpdated:2020/7/8