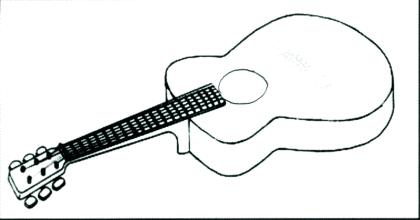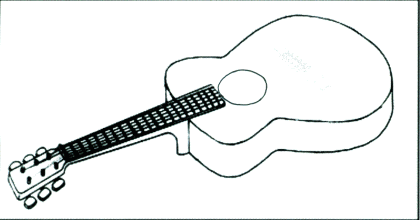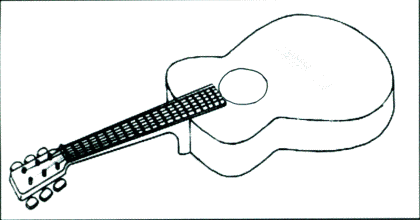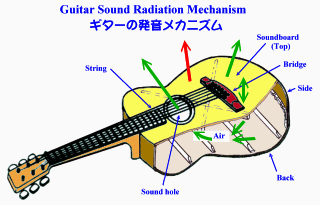「ギターの振動を解析してみる・・・」と言う、若い頃からの積年の大きな目標に取り組んで、このテーマを書いて見ました。
多少、こじつけの理屈も入っているとはおもいますが、何台かのギターでの実際の実験結果や、参考とした、2自由度振動系
振動工学の理論(注)を当てはめて見ると、「当たらずとも遠からず・・・」
、納得できる結果は得られたと考えております。
「ギター ウルフトーン」で検索をかけると、数百にものぼるページがヒットし、ギタープレーヤーの関心の強さを物語っているテーマでは有りますが、この種の
解析例は、ごく一部の海外の工科大学のサイトでしか公開されている例がありませんでしたので、敢えて生データや画像・映像なども含めて公開させていただきました。
何方のお役に立つか・・・、それは分かりませんが、プレーヤーの方、あるいは、ギター製作家の方にとって、何らかでもご参考になれば幸いです。
今まではTop (サウンドボード) の共振
が、ある意味、これは良い事・・・と思っていた訳ですが、
逆に、ボリューム感のある大きな音である事が、ヒビリや雑音の発生、音色やピッチにも影響も及ぼしていた・・・と言う、予想外の結果でした。 共振
と言う振動現象は、一見良いもの・・・と考えられがちですが、工学的に見ると、例えば、地震で超高層ビルが共振して大きな揺れをもたらす・・・その対策には莫大な労力と費用を必要とする、あるいは、自動車などでも、高速で安定して走行するためには、車体やサスペンションの制振(共振をいかに防ぐか・・・と言うもの)に多大の労力を費やしているのが最先端技術の一端です。 ギターのような弦楽器の場合、僅かな弦の振動を如何に大きな空気振動に変換するか・・・と言う目的から共鳴胴が付けられている訳ですが、全てを良い方向だけに導いてくれる物は、神様もそう簡単には与えてくれなかったようです。
どうしたら、この「ギターの宿命」から逃れられるか・・・は、現時点では答えは出
ていません。 この「ギターの宿命」をブレークスルーする新たな考えが生まれてくる事を望みます。 例えば、Top(表板)の裏に貼り付けられている所謂ブレースの構造を変える・・・、サウンドホールの大きさ・形状を変える.・・・など、考えられる事は多々有るとおもいます。
(注)
サウンドホールを極端に小さくしたギターや、なくしてしまったギター
、あるいは、サイズ・ブレーシングに工夫を凝らして、「ウルフトーンを低減した・・・」とうたっているギターなどは既に有りますが。
モード
(0)
や モード (0,0)
の強すぎる共振を少しでも軽減するために、Xブレーシングに、更に、真ん中・縦に思い切ってもう一本強力なブレースを設けて、XYコンビネーションブレースにする・・・
、あるいは、バイオリンやチェロなどの弦楽器のように、縦に長い・強力なバスバーを配置する・・・
、また、共鳴胴の強すぎるヘルムホルツ共振現象を少しでも低減するために、何処かに、空気抜き(ガス抜き)の穴をあける・・・と言うような、奇想天外の構造も考えられるとおもいます。
是非、これからのギターメーカーや製作家の方には、色々とチャレンジして頂ければ・・・と思う次第です。
ちなみに、空気抜き(ガス抜き)の穴を開けたり、サウンドホールの位置や形状を変えて工夫しているギターについて調べてみましたら、海外ルシアー製作のギターでは、すでに色々なものが試されていることがわかりました。 下の、番号をクリックしてご覧ください。
ProfessionalLuthier.com より。
1 Applengata
2 Beardsell
3 Alejandro
4 Cornerstone
5 Fleshman
6 Florian
7 Hemken
8 Hill
9 James
10 Marchione
11 McKnight
12 D.L.Noble
13 Soloman
この数の多さをみると、海外ルシアーたちの、より良い音を求める研究熱心さには頭が下がります。
中森明菜の歌を引用すれば 「飾りじゃないのよ・・・この穴は・・・」 と云ったところでしょうか。
終りに、今回掲載した内容に、疑問点、あるいは、「これは間違っている・・・」と言うような点がありましたら、是非お気軽にご意見などを、こちらから、お寄せ頂ければ幸いです。
また、大学や企業の研究部門でこの種の研究をなさっておられ方がありましたら、是非ともご意見・ご感想を頂ければ幸いです。(注)
お読み頂きまして、有り難う御座いました。
2007-2-15 工房ミネハラ 原田峰雄
(注)現在のコンピューター解析による振動工学では、たった二つの自由度の解析ではなく、数十・数百自由度の解析が可能となっていますので、この分野に興味ある方には、引き続きもっとディーテイルな解析にチャレンジして頂けれは・・・と思う次第です。
Copyright (c) Lab Minehara,
All rights reserved.

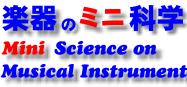
![]()