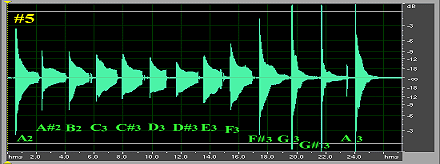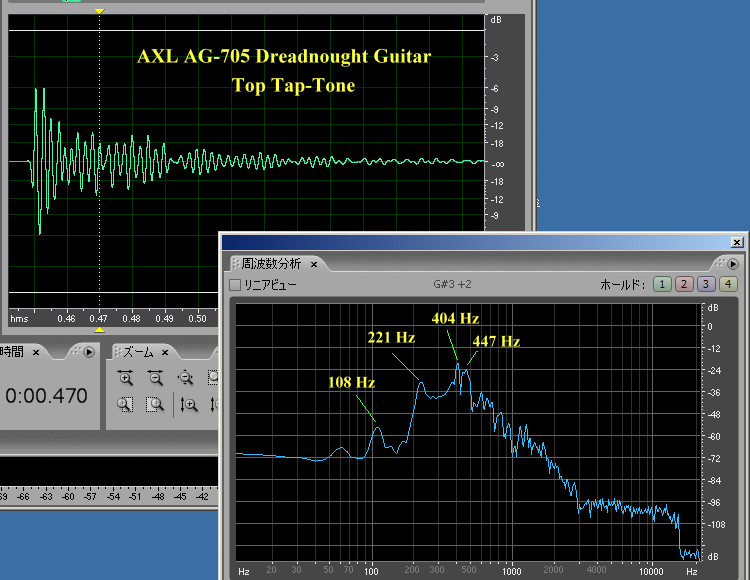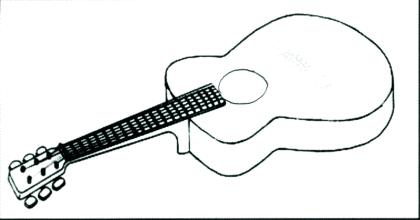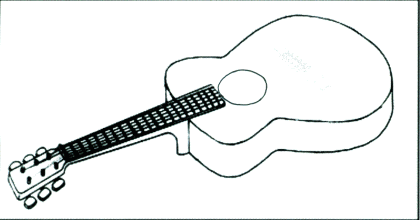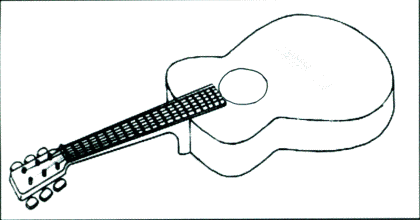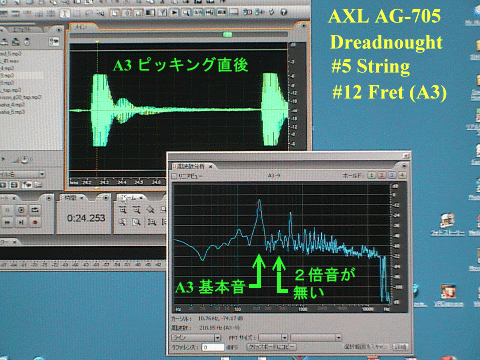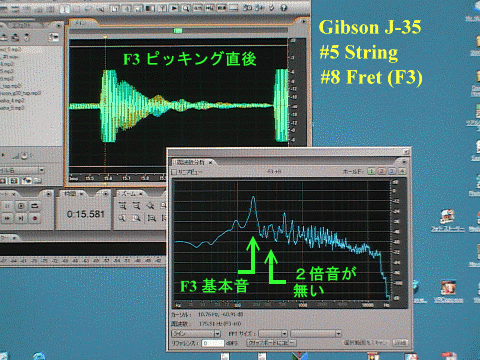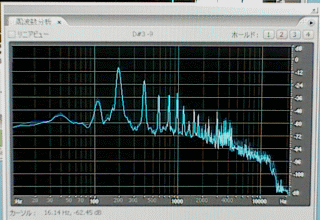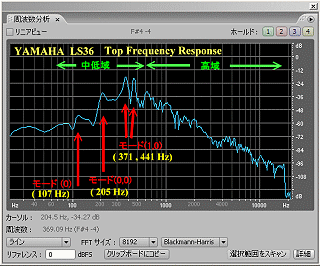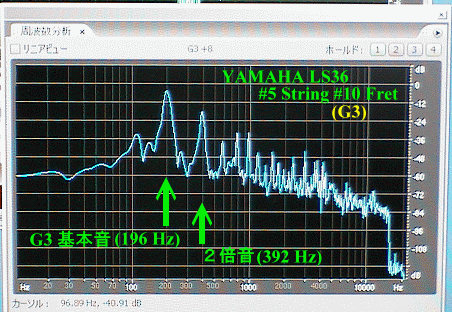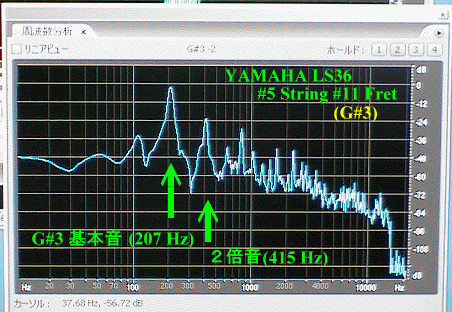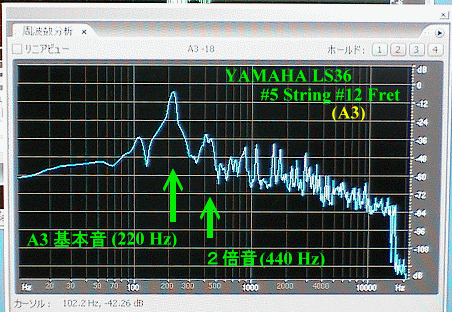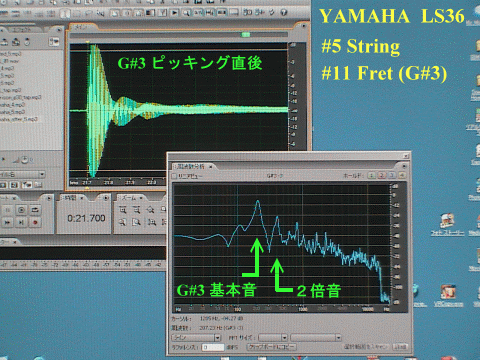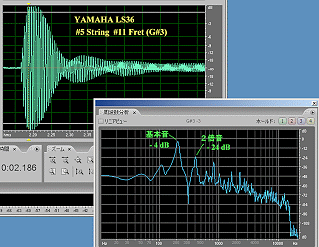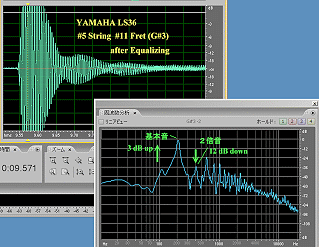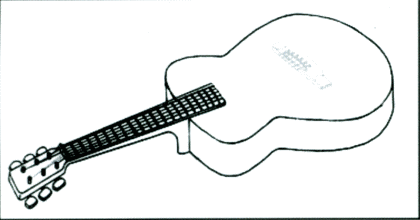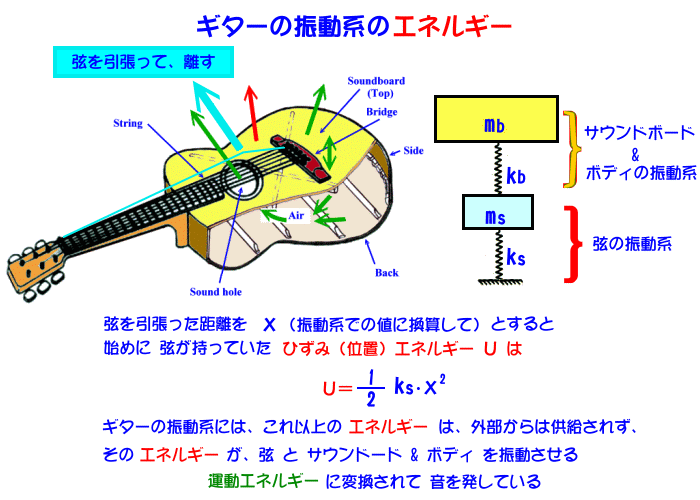|
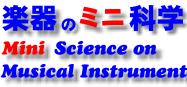 ギターボディー 振動の力学 (10) 第10章 ウルフトーンの功罪 |
![]()
前章 までは 大きな音を出すにも拘わらず、余韻の 音色が詰まった感じに変化する 音について調べてきました
所謂、ウルフトーン です。
このような現象を引き起こす特定の音、 そこには、どんな メリット、ディメリット があるのでしょうか。
”功”・・・メリット、 それは、紛れもなく、太く、確りした、大きな音 を出してくれていること・・・には、間違いありません。 特に、#4, #5, #6 弦 辺りですので、低音として、大きな音である事は重要です。
![]() ウルフトーン を
生ずる音の ”罪”・・・ディメリット とは
ウルフトーン を
生ずる音の ”罪”・・・ディメリット とは
このサウンドは、一番初めのページでご紹介した下記のサウンドの、終りの 3っの音 #5 弦の、 G3 G#3 A3 の音だけを切り出したものです。
すなわち、今まで、事例として来た、Yamaha LS36 に於いて、最もウルフトーンの強い音と考えられます。
チェロなどの弦楽器の場合でも、同じ音でも、弦の短いところのポジションの方が、ウルフトーンは激しく出ます。 ギターの場合も、ハイポジションの音の方が、激しく出ていますので、 #5 弦をサンプルとして取り上げました。
この
A の、前半の 3っの音 は、レコーディングされたままで、何の手も加えて有りません。
しかし、 後半の 3っの音 は、前半の 3っの音 に少し手を加えて有ります。 これからのテーマをお読みいただくと、それらの差がご理解いただけるとおもいます。
始めは、こちらの、叩けば分かる 共振周波数・・・、のところで、
AXL でタップトーンデーターを示したギターです。
Dreadnought Size のギターで、Top のみ単板仕様の、そんなに値段の高いギターではありません。
始めに、この
(AXL #5 String All Sound) をご覧下さい。
このギターの、 #5 弦の開放弦 A2 から、#14フレット B3 までを弾いたもののビデオです。
#12フレット A3 の音に、ウルフトーンが最も激しく出ている事がお分かりいただけると思います。
このギターの、この、タップトーンサウンド
AXL を周波数分析してみますと、下のようになっていました。
221 Hz すなわち A3 の付近に、モード (0,0) 共振点 があると考えられます。
従って、#12フレット A3 の音に、ウルフトーンが最も激しく出ている事は、当然の事として分かります。
ここで、もう少し、その様子を細かく見て見ましょう。
このギターの #5 弦の開放弦 A2 のみの
(AXL #5 String A3) をご覧下さい。 これが、実際の映像とサウンドです。
下の画像をクリックしてご覧ください。
これは、#12フレット A3 の音について、その音に含まれている周波数成分を、アニメーションで表示したものです。
アニメーションが、始めに止まっているところは、弦を ピッキングした直後 0.05 秒 辺りの周波数成分を示しています。
良くご覧いただくと分かるとおもいますが、2倍音である 440 Hz 辺りの周波数成分が、 ありません。
少し時間が経つと、今までもご説明して来ましたように、基本音である 220 Hz 辺りの周波数成分が 急に減衰 して行き、その後に、2倍音である 440 Hz 辺りの周波数成分が、やっと見えてくる・・・
と言えませんでしょうか。
下の画像をクリックしてご覧ください。
では、このビデオで、
(Gibson J-35 #5 String #7-#10 Fret Sound) このギターの、 #5 弦の、#7フレット E3 の音から、#10フレット G3 の音だけを、ビデオでご覧下さい。
基本音 の周波数成分が、強烈に強く出でいることがお分かりいただけると思います。
アニメーションが、始めに止まっているところは、弦を ピッキングした直後 0.05 秒 辺りの周波数成分を示しています。
良くご覧いただくと分かるとおもいますが、2倍音である 350 Hz 辺りの周波数成分が、 ありません。
少し時間が経つと、今までもご説明して来ましたように、基本音である 175 Hz 辺りの周波数成分が 徐々に減衰 して行き、その後に、2倍音である 350 Hz 辺りの周波数成分が、やっと見えてくる・・・
と言えるとおもいます。
このギターは、胴のサイズが大きく、従って、今まで事例として来た、Yamaha LS36 や、上の 事例Ⅰ のギターより、モード (0,0) 共振点 が低い周波数に有ることは、自ずと分かります。
ここで、 事例Ⅰ と 事例Ⅱ の共通点を見てみましょう。
何れのギターも、
弦を ピッキングした直後 0.05 秒 辺りの 周波数成分 には、弦の振動数の、 2倍音 の周波数成分 が、 ない 。
または、
共振点 モード (0,0) は立ち上がるが、共振点 モード (1,0) の立ち上がりが、阻害されてしまう。
こんな現象があることが分かりました。
今までこのシリーズのデーター事例として来た、Yamaha LS36 の場合は、どうだったののでしょうか。 それを、バックチェック (振り返って、もう一度調べてみる) ことにしました。
このギターの、 #5 弦の、 G3 から A3 の、3っの音の周波数成分について、もう少し詳細に
(YAMAHA #5 String #11 Fret Sound G#3) で見てみる事にしました。
左の画像をクリックすると、ビデオをご覧いただけます。 これが、実際の映像とサウンドです。Windows Media Player の場合、<再生><再生速度><遅く>にすると、音は若干変化しますが、動いている波形の違いは良く分かります。
#5 弦の、 G3 G#3 A3 の、3っの音を、2回繰り返しています。
この、3っの音の周波数成分の大きさ、立ち上がりや減衰の速さを見ると、次のようなことが言えると思います。
その前に、このギターの共振点のモードと共振周波数について、下の画像をクリックしてご覧になっておいて下さい。
Note ピッキングした直後 の 周波数成分
基本音 2倍音 G3 基本音 ( 196 Hz ) は、 モード (0,0) ( 205 Hz ) 付近にあるため、
大きいレベルを示すが、減衰も相当早い。
周波数の差は、9 Hz
2倍音 ( 392 Hz ) は、 モード (1,0) ( 371 Hz ) 付近にあるため、
大きいレベルを示すが、減衰も相当早い。
周波数の差は、21 Hz
G#3 基本音 ( 207 Hz ) は、 モード (0,0) ( 205 Hz ) と重なるため、
大きいレベルを示し、減衰も非常に早い。
2倍音 ( 415 Hz ) は、 モード (1,0) 付近にあるが、
( 371 Hz ) ( 441 Hz ) には重ならず、
大きいレベルを示し、減衰も穏やか。
周波数の差は、44 Hz , 26 Hz
A3 基本音 ( 220 Hz ) は、 モード (0,0) ( 205 Hz ) 付近にあるため、
大きいレベルを示すが、
G3 の場合よりも、中心から外れているので、
減衰の程度はやや緩やか。
周波数の差は、15 Hz
2倍音 ( 440 Hz ) は、 モード (1,0) ( 441 Hz ) とほぼ一致し、
ピッキング直後
2倍音 の周波数成分 が、立ち上がらない。
その後、減衰は穏やか。
周波数の差は、1 Hz
上の表で、 事例Ⅱ の所が、上の、 事例Ⅰ や 事例Ⅱ と大変良く似ています。
共通点は、
基本音 が モード (0,0) 付近の共振点に重なると 基本音 は 、 強烈 に立ち上がるが、
その 2倍音 が モード (1,0) 付近の共振点と重なっ場合、
ピッキング直後 の 2倍音 の 立ち上がりが、阻害されてしまう。
と、言えるかも知れません。
この現象は、こちらで考えた、ダイナミックダンパー Dynamic Damper と言う考えでも説明が付く現象と思われます。
このギターの、ウルフトーンが最も激しく出ている #5 弦の、 G#3 の音について、 事例Ⅰ や 事例Ⅱ と同じく、アニメーションを作ってみました。
#5 弦の、 G#3 のみの
(YAMAHA #5 String #11 Fret Sound G#3) をご覧下さい。 これが、実際の映像とサウンドです。
下の画像をクリックしてご覧ください。
アニメーションが、始めに止まっているところは、弦を ピッキングした直後 0.05 秒 辺りの周波数成分を示しています。
良くご覧いただくと分かるとおもいますが、2倍音である 415 Hz 辺りの周波数成分は、チャンと現れています。
少し時間が経つと、今までもご説明して来ましたように、基本音である 207 Hz 辺りの周波数成分は 徐々に減衰 して行きますが、その後も、2倍音である 415 Hz 辺りの周波数成分は、 ある程度持続 しています。
このギターの場合は、余韻の 音色が詰まった感じ にはなっていますが、 事例Ⅰ や 事例Ⅱ のような、 極端な音の詰まりや、ビビリ音 はありません。
![]() モード
(0,0)
共振が 強すぎると、どうなるか・・・
・・・これは、一つの仮説ですが、模擬的に検討してみました。
モード
(0,0)
共振が 強すぎると、どうなるか・・・
・・・これは、一つの仮説ですが、模擬的に検討してみました。
この 冒頭の
A の、前半の 3っの音 は、レコーディングされたままで、何の手も加えて有りません。
それに対して、 後半の 3っの音 は、前半の 3っの音 に 少し手を加えて有ります。 それは、
前半の 3っの音 に対して、Adobie Audition 2.0 で音の波形に、Graphic Equalizer を掛けて、下表のように、特定の周波数成分の音の大きさ(強さ)を変えてみました。
200 Hz 基本音 +3 dB 事例Ⅰ 事例Ⅱ のギターのように、基本音 を極端に強くして、 2倍音は減少させた。
400 Hz 2倍音付近 -16 dB 500 Hz 2倍音付近 -6 dB
その結果、この
A の、前半の 3っの音 が、後半の 3っの音 のように変わり、 事例Ⅰ 事例Ⅱ のギターと同じような、 極端な音の詰まり感 がで出来ました。
#5 弦の、前半の G#3 と、後半の G#3 の周波数成分を較べて見ましょう。
前半の G#3 何の手も加えてない状態
後半の G#3 Graphic Equalizer を掛けた状態
ここで言えることは、
基本音、 2倍音 の周波数成分 の音の大きさ(強さ)が、 僅か変わっただけで、音色は大きく変わってしまう。
またまた、疑問点が出てきてしましました。
1. 弦を ピッキングした直後 0.05 秒 (1/20 秒) 辺り・・・といえば、弦の振動は、スタートから 20回程度 しか起こってない、極初期の段階です・・・が、
そのような極初期の段階で、2倍音の音が含まれる モード (1,0) 共振点 の立ち上がりを阻害する 何らかの陰の力 が働いているのでしょうか。
それは、
こちらで考えた、ダイナミックダンパー Dynamic Damper となる陰の力 が働いたためと考えられます。
2. モード (1,0) 共振点 には、今まで考えてこなかった別な物が有るのでしょうか。
疑問点 の 2.に関しては、別な物が有る・・・と考えられます。 モード (1,0) 共振点 には、もう一つ、あるいは、更に違った物が有りそうだ・・・。 振動工学的には、存在します。
アニメーション モード名 振動の様子 共振点の振動数 今まで考えてきた形 モード (1,0) ブリッジを境にして、 表板(Top) の上半分と下半分が交互に上下に振動する
モード (0,0) の 2倍 新たな考え方の形 モード (1,1) ブレースなどに沿った領域を境にして、 表板(Top) の 右半分と左半分が交互に上下に振動する
モード (0,0) の関連が無い、独立
今回、 事例Ⅰ と 事例Ⅱ で起こっている現象が、新たな考え方の形・・・モード (1,1) 共振点 によるものか否か・・・については、まだ検討が十分に進んでおりませんので、ここでの説明は避けます。
疑問点 の 1.に関しては、次の段落のように考えると、辻褄が合います。
![]() エネルギーは一定・・・強い所が有れば、どこかに、弱いところが出来て当然・・・・・・と言う考え方です。
エネルギーは一定・・・強い所が有れば、どこかに、弱いところが出来て当然・・・・・・と言う考え方です。
下の絵は、ダイナミックダンパー と言う 考え方の時に出てきた絵と似ていますが、ここでは、弦を弾いた瞬間・・・について考えます。
この考え方は、エネルギー保存則 と呼ばれます。
ギターの弦を弾く・・・と言うは、指かピックで弦を横に引張って、それを、瞬間的に離し、弦を振動させます。 弦の振動が、サウンドボードに伝わって、サウンドボードが共振し始めて、大きな音を出します。
弦を横に引張るには、ある程度の力が必要です。 引張られた弦には、ひずみ(位置)エネルギー U が蓄えられます。 弦が指から離れた瞬間から、弦には何らエネルギーは供給されません。
供給されないどころか、逆に、空気抵抗や木材内部の摩擦・・・などの、様々な抵抗に合い、どんどん減少してしまうので、やがて、弦は振動を止めてしまうのです。
要するに、始めに有った、ひずみ(位置)エネルギー U によって、弦が振動したり、サウンドボードが振動(共振)したりする 運動エネルギー が発生します。
サウンドボードの振動(共振) について考えた場合、最初に大きな振動として誘起される モード (0,0) 共振 が 大き過ぎる と、その他の モード (1,0) 共振 などへ回されるエネルギーは、少なくなってしまう・・・と考えられます。
従って、今回の 事例Ⅰ や 事例Ⅱ のギターで発生している、
基本音 が モード (0,0) 付近の共振点に重なると 基本音 は 、 強烈 に立ち上がるが、
その 2倍音 が モード (1,0) 付近の共振点と重なっ場合、
ピッキング直後 の 2倍音 の 立ち上がりが、阻害されてしまう。
この現象は、
モード (0,0) 共振 が 大き過ぎる ために、その上の モード (1,0) 共振 へ回される エネルギーが減少 してしまった。
そのために、モード (1,0) 共振点 付近の音の周波数成分が、瞬時に立ち上がらなかった・・・。
モード (0,0) 共振 が、やや小さくなる頃からは、モード (1,0) 共振 も維持される。
あるいは、
モード (0,0) 共振 が 大き過ぎる ために、その上の モード (1,0) 共振 を打ち消す、 位相(力の向き)が逆の大きな力 が瞬間的に働き、
モード (1,0) 共振点 付近の音の周波数成分が、瞬時に立ち上がらなかった・・・。
モード (0,0) 共振 が、やや小さくなる頃からは、モード (1,0) 共振 も維持される。
位相(力の向き)が逆の大きな力 ・・・これが、こちらで考えた、ダイナミックダンパー Dynamic Damper となる 陰の力
と考えられます。
この章の、冒頭の
![]() ウルフトーン を
生ずる音の ”罪”・・・ディメリット とは
を、纏めてみましょう。
ウルフトーン を
生ずる音の ”罪”・・・ディメリット とは
を、纏めてみましょう。
ギターの形、サイズ、材質、ブレース構造・・・その他、色々なファクターが影響している・・・と考えられるが、
表板(Top)固有 の 板の共振特性 によって発生する モード (0,0) 200 Hz 付近 の共振 が 強すぎる 場合は、
余韻が極端に短い音 ウルフトーン が強く 時には、 Buzz (ビビリ音 ・雑音) を発生させてしまうギターもある。
と言えるでしょう。
他の音は申し分ないのに、特定の音に来ると響かない・・・と言うのは、フィンガーピッキングをすることの多いギターリストにとってはちょっと残念なギターかも知れませんね、
そういう観点から見ると、
このシリーズのデーター事例として来た、
Yamaha LS36 は、 #5 弦の、 G3 G#3 A3 辺りの音には、多少の ウルフトーン が見られますが、
事例Ⅰ や 事例Ⅱ のギター程、極端なものでなく、全体として、ある程度のバランスがとれたギター・・・と言えるの かも知れません。
それは、皆様のご判断にお任せします。
それじゃ・・・、如何したら、もっと良いギターは作れるの・・・
それ は、また、別なテーマで考えたいと思っております。
この続きは、続き(11) をご覧下さい
ギターボディー 振動の力学 続き(11) へ
■Copyright (c) Lab Minehara, All rights reserved. このページに掲載の全てのコンテンツ (記事、画像データ・数値データなど) の無断転載 ・公開等はお断りします。
工房ミネハラ
Mineo HaradaUpdated:2007/2/10